| 悠久4500年という中国薬膳のなかで冬虫夏草や霊芝の陰に隠れていたキクラゲが、ようやく日本で、その実力を顕し始めた。 |
 |
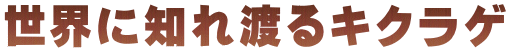 |
| 広葉樹の朽木に寄生するキクラゲは1400年前の漢王朝の時代から薬膳料理の食材として有名で「木耳」と表記されて人工栽培されていた。 英語圏でキクラゲは「Jewʼs Ear (ユダの耳)」とも呼ばれ、その昔、キリストを裏切ったユダがニワトコ(庭常)の木で首を吊った際に、ちょうどその木に発生していたキノコだったと言われている。したがってある地方のクリスチャンたちは、キクラゲを忌み嫌って食べない習わしがあるそうだ。 また日本では食感がクラゲに似ていることから「木のクラゲ」といわれたのが、キクラゲという名前の由来だと言われている。 |
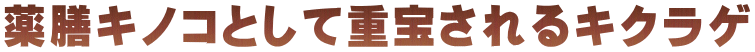 |
| キクラゲ多糖体 |
| 中国で木耳は五木(槐、楡、桑、楮、柳)に発し、気を益し、飢えず、身を軽くし、心を強く、痔を治すなどの薬効があるとされており、鍋物や炒め物の副材として重宝されていた。また鉱山で働く作業員は、給料日になると1ヶ月分の木耳を支給されて家庭で食べる習慣がある。これは木耳の肺内浄化作用が顕著であるということである。 栄養としては、キクラゲ多糖体という成分が多く含まれている。これはキクラゲ特有の高分子多糖体で、免疫システムを担う免疫細胞を活性化させたり、NK細胞の増殖を促す「サイトカイン」という物質をつくるなどの期待もあり、コロナ禍においては特に注目されている成分である。またビタミンDや鉄分、カリウム、マグネシウムなどミネラル類の含有率も高いので、これらの補給源としても貴重な食材となる。 |
| 血栓を防止 |
| 新型コロナを例にしましょう。コロナ感染するとその影響が全身に及んで臓器障害を引き起こし、生命が脅かされるような状態を敗血症と呼んでいます。そのような場合には、血栓形成が全身で起こりえます。 |
| キクラゲの栽培手順 |  |
| 冬虫夏草 | 霊 芝 | キクラゲ | マイタケ | 組織紹介 | |

 |
薬膳として有名なキクラゲ|食事革命
Copyright (C) 2020/05/01-2024/09/04
FOOD INNOVATION ORG..